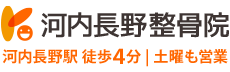仕事中や通勤中のケガ、整骨院で労災適用は可能?具体例でわかる対応ガイド

「仕事中に腰を痛めた」
「通勤中に転倒して足をくじいた」
──そんなとき、整骨院に受診したいと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし気になるのが、「整骨院で労災って使えるの?」「どうやって申請すればいいの?」という点です。
労災保険は、業務中や通勤中のケガに対してかかる費用をカバーしてくれる制度ですが、病院だけでなく整骨院でも適用できる場合があります。
ただし、手続きの流れや整骨院の対応可否など、事前に知っておくべきポイントがいくつかあります。
この記事では、具体例を交えながら「整骨院で労災を使う方法」と「気をつけるべき注意点」をわかりやすく解説していきます。
1. 仕事中・通勤中のケガは整骨院で施術できる?
● 労災保険の基本的な仕組みとは?
労災保険(正式名称:労働者災害補償保険)は、業務中または通勤中に発生したケガや病気に対して、費用負担や休業補償などの給付を受けられる公的保険制度です。
雇用されている労働者であれば原則としてすべての人が加入しており、パートやアルバイトでも対象になります。
● 整骨院で対応できる症状の具体例
整骨院で労災施術が可能な症状には、以下のようなものがあります:
- 通勤中に自転車で転倒して肩を捻挫した
- 仕事中に重い荷物を持ち上げてぎっくり腰になった
- 職場の階段で滑って膝を強く打った
こうした打撲・捻挫・挫傷などの“筋骨系の外傷”に対して、整骨院での手技療法や電気施術が効果的なケースが多く、労災の対象として認められます。
2. 労災が適用されるケース・されないケース
● 労災が適用される典型例
労災保険が適用されるには、「業務中」または「通勤中」の災害であることが条件です。
以下のようなケースは、労災として認定されやすい典型例です。
- 通勤中の事故:出勤途中に自転車で転倒し、肩を捻挫した
- 職場での転倒:床が濡れていたため滑って転倒し、膝を強打した
これらのケースでは、会社が労働時間・業務内容・出退勤の経路を把握していることが多く、労災申請もスムーズに進む傾向があります。
● 労災が適用されないケース
一方で、以下のようなケースでは労災が認められないことがあります。
- 業務外でのケガ:昼休みに私用で外出中に転倒した
- 寄り道中の通勤災害:帰宅途中にカフェに立ち寄った後の移動中に起きた事故
- 私的な理由での行動中:勤務時間外に職場で筋トレしていてケガをした
このようなケースでは、「業務遂行性」や「通勤の合理性」がないと判断されるため、労災対象外とされる可能性があります。
3. 労災保険を整骨院で使うための手続きの流れ
● 会社への報告が第一ステップ
ケガをしたら、まず職場の上司や労務担当に速やかに報告しましょう。
労災は自己判断ではなく、会社側の協力があって初めて正式な申請が可能になります。
● 柔道整復師用「様式第7号」の提出が必要
整骨院で労災を使う場合、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第7号)」という書類を会社に作成してもらう必要があります。これは、病院用とは異なる柔道整復師専用の労災申請書類です。
会社が様式第7号を発行してくれたら、それを整骨院に提出することで、労災扱いでの施術がスタートできます。
● 費用は労災保険で全額カバーされる
労災が正式に認められると、自己負担は原則0円です。自由診療ではなく、保険施術として適用されるため、金銭的な不安を感じることなく施術に専念できます。
4. 実際の事例紹介:このようなケースで労災が使えました
ここでは、整骨院で労災が適用された具体的な事例をご紹介します。実際のケースを知ることで、ご自身の状況に照らし合わせやすくなります。
● 通勤中の自転車事故で肩を負傷したケース
状況:
30代男性。通勤中に自転車で段差に乗り上げて転倒し、右肩を強く打撲。整形外科で骨に異常はないと診断されるも、痛みが残るため整骨院に通院。
対応:
勤務先に報告後、様式第7号を会社から受け取り整骨院に提出。労災適用で施術が開始され、電気療法と手技療法で3週間の通院。
ポイント:
通勤中という明確なシチュエーションであり、会社も労災申請に協力的だったため、スムーズに手続きが完了。
● 業務中の荷物運搬でぎっくり腰に
状況:
40代女性。職場での荷物の持ち上げ作業中に急な腰痛を発症。整形外科で「急性腰痛症」と診断され、仕事を一部制限される。
対応:
労災申請のため、会社に状況を説明し、整骨院での施術を希望。申請書類を提出し、労災として承認。週2回の通院で徐々に回復。
ポイント:
ぎっくり腰のような明確な外傷性の症状でも、業務中であれば労災の対象となる。
● 職場での転倒による膝の打撲
状況:
50代男性。勤務先の通路にこぼれていた水に足を取られ転倒し、膝を強く打つ。歩行に支障が出たため整骨院へ。
対応:
目撃者もいたため会社が状況を把握しており、すぐに様式第7号を作成してくれた。整骨院での治療もスムーズに進行。
ポイント:
職場環境が原因のケガであれば、証明しやすく労災申請もしやすい。
5. 労災を使うときに知っておきたい注意点
整骨院で労災を使う際には、制度上のルールや手続きの順序をしっかり押さえておくことが大切です。
間違った認識や準備不足があると、申請が通らなかったり、自己負担が発生してしまうことも。
ここでは、特に注意しておきたいポイントを紹介します。
● 整骨院によっては労災対応していない場合もある
実は、すべての整骨院が労災保険に対応しているわけではありません。
労災指定の取り扱いがない院では、たとえ労災の対象となるケガであっても、自費診療扱いとなることがあります。通院前に「労災に対応していますか?」と電話などで確認することをおすすめします。
● 自己判断で通院を始めると後から手続きが難しい
ケガをしてすぐ整骨院に行きたくなる気持ちはわかりますが、会社に報告する前に通院を開始してしまうと、労災が認められにくくなる場合があります。
特に、様式第7号(柔道整復師用)を整骨院に提出せずに通院を始めた場合、費用が自己負担になる可能性もあるため注意が必要です。
● 会社との連携も非常に重要
労災申請には、会社の協力が不可欠です。
「書類の発行に時間がかかる」「労災扱いにしてもらえない」といったトラブルを防ぐためにも、まずは上司や労務担当に速やかに報告し、必要な書類や流れを確認しましょう。
6. 労災対応可能な整骨院の選び方
労災が適用されるケガであっても、整骨院側が労災に対応していない場合は保険を使うことができません。
スムーズに施術を進めるためには、初めから労災対応可能な整骨院を選ぶことが重要です。
以下のポイントを参考に、信頼できる整骨院を見極めましょう。
● 「労災指定整骨院」かどうかを確認
まず最も重要なのは、その整骨院が労災保険の取扱いをしているかどうか。
労災指定を受けていれば、様式第7号を提出することで、患者さんは費用負担なく施術を受けることが可能です。
以下の方法で確認できます:
- 整骨院のホームページに「労災保険対応」「労災指定」の記載があるかチェック
- 電話で「労災保険の取り扱いはしていますか?」と事前に確認する
● ホームページでチェックすべき3つのポイント
整骨院のサイトで以下の情報が明記されていれば、労災対応が期待できます:
- 「労災保険取り扱い」や「交通事故・通勤災害にも対応」と書かれているか
- 「初めての方へ」「保険について」などのページが整備されているか
- アクセス・診療時間が明記され、信頼性が高い印象か
● 初診前に問い合わせるべきこと
来院前に、以下の点を整骨院に確認しておくと安心です:
- 労災保険に対応しているか
- 様式第7号を提出すれば手続き可能か
- 予約の必要有無、診療時間など
また、どのような症状に対応しているかも確認しておくと、治療方針とのミスマッチを防げます。
7. まとめ:労災の正しい知識で安心して整骨院を活用しよう
仕事中や通勤中にケガをした場合、整骨院での施術にも労災保険が適用できるケースが多くあります。
しかし、そのためには、
「どんな場合に労災が使えるのか」
「どんな手続きが必要なのか」
「整骨院側が対応しているか」
といったポイントを正しく把握しておくことが大切です。
この記事では、
- 労災保険が整骨院でも使える理由と対象となる症状
- 労災が適用される・されないケースの違い
- 必要な手続きと、会社との連携の重要性
- 実際の事例紹介
- 整骨院を選ぶ際のポイントや注意点
などを具体的にご紹介しました。
特に、初動で【会社への報告】と【整骨院への確認】を怠らないことが、スムーズな労災申請のカギとなります。
整骨院での施術は、手技や物療による回復を目指す点で、病院とは異なる魅力があります。
労災の正しい知識を持っていれば、身体の回復と仕事への復帰を安心して目指すことができるはずです。
もし、ケガをして「労災が使えるか不安…」という場合は、早めに整骨院や会社に相談することをおすすめします。